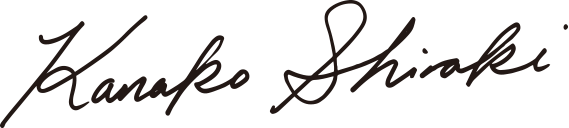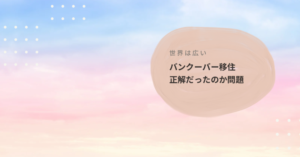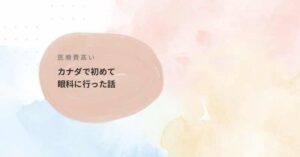最近、私が働くカナダの会社にインターンが入ったので、なんとなく教育担当というかプロジェクトにフィードバックしたり、仕事のやり方をお伝えしたりしています。私は基本的には 「人の可能性を信じたい」 タイプです。でも、インターンの子に大事なポイントを伝えても、返ってくるのは言い訳やできない理由だったりします。
これまでのキャリアの中で、新卒の後輩が入社当初は正直なところ仕事ができず、どう指導すればいいのか困ったこともありました。しかし、そんな後輩たちも 4〜5年経つ頃には立派にリーダーを務めるようになっていました。
新人研修やマネージャー研修など、人を育てる側にたったこともたくさんありますし、私自身も研修を通して成長するのが好きでした。だからこそ、教育の力は大きい と感じています。
しかし、一方で 「成長するかどうかは本人次第」 という現実もあります。
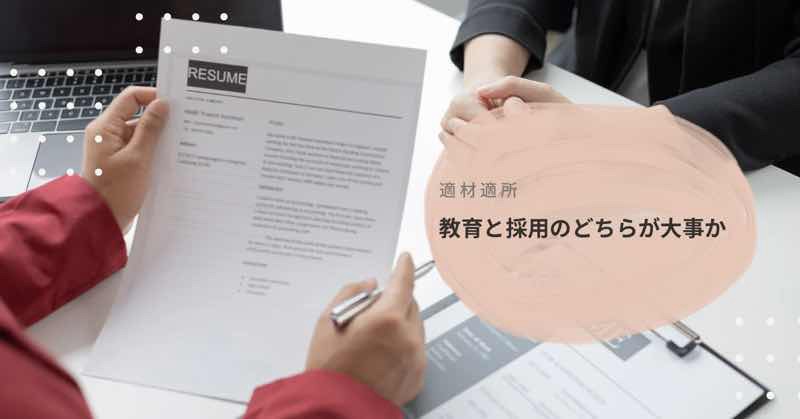
どんなに会社が良い教育の場を提供しても、フィードバックをして改善を求めても、本人に聞く耳ややる気がなければ成長につながりません。
だからこそ、私は「人の可能性を信じたい」と思いつつも、結局は 「採用が大事」 だと感じます。
部門別採用の良さ
私が最初に入社した会社では、「部門別採用」 を取り入れていました。
• 採用の段階で どの部署に配属されるかが決まっている
• 配属予定の部署の社員が面接官を務める
• 採用後は、基本的にその職種の専門性を磨いていく
当時は特に何も思っていませんでしたが、今振り返ると この採用方法は理にかなっていた と思います。
なぜなら、最初から部署の仕事に合うかどうか、人柄がチームにマッチするかを見極められる からです。
仕事はやはり 適材適所 です。
例えば、データ分析が必要な部署に、細かいデータのチェックや法則性を見出すのが苦手な人を配属したとします。
もちろん、時間をかければできるようになるかもしれませんが、苦手なことを克服するのは簡単ではありません。
一方で、最初から データ分析が好きな人 であれば、喜んでその業務に取り組むことができます。
結果的に、本人の成長スピードも速くなり、組織としてもより高いパフォーマンスを発揮できるでしょう。
もちろん、違う職種を経験することで得られる知識もあります。
ジェネラリスト的なキャリアを歩みたいなら、それは大いに価値があるでしょう。
しかし、専門性を磨きたい人にとっては遠回りになることも多いのが実情です。
採用面接で私が見ていたこと
採用面接を担当するようになったとき、私は「何を基準に見るべきか?」を深く考えるようになりました。
スキルはもちろん大事ですが、私は特に以下のポイントを重視していました。
仕事に対する「向き・不向き」
• その人が 楽しめる仕事 なのか?
• 会社として 成長をサポートできる領域 なのか?
学ぶ姿勢・改善力
• 指摘を受けたときに、素直に改善できる人か?
• 受け身ではなく、自ら成長しようとする姿勢があるか?
チームとの相性
• チームの雰囲気に合う人か?
• 協力しながら仕事ができるか?
カナダは今、買い手市場で一つの採用募集を出すとあっという間に100人くらいの応募者が集まってしまいます。小さな会社でもです。
一人一人のレジュメを見るだけでもかなり大変な作業です。まずはスキルや経験で比較されますが、面接まで行った人は最後はやはりチームとの相性、会社との相性が見られるように感じます。
私の今働いている会社は全部で25人くらいの小さな会社なので、どうしても細かく仕事を教えている余裕がありません。そのため、即戦力であることはもちろん、自分で仕事を責任を持って進められる人材が必要です。
教育 vs. 採用 どちらが重要か?
結論から言えば、「両方大事」 だと思います。
ただし、教育は本人にやる気がなければ意味がありません。
私が役員を務める日本のIT企業では、他社では採用がなかなか厳しい中、毎週何十もの応募者が集まります。問題は、会社に根付いてくれる人が少なく、数年すると辞めてしまうことです。定着率をどう上げるかが、教育で解決できる部分もあるのかもしれませんが、やはり採用の段階で「その仕事に向いているか?」「チームに合っているか?」「本人に成長意欲があるか?」をしっかり見極めることが大切だと思います。
適材適所の採用ができれば、その後の教育もより効果的になります。
人の可能性を信じつつも、「採用がすべてのスタート地点である」ことを、最近強く思います。