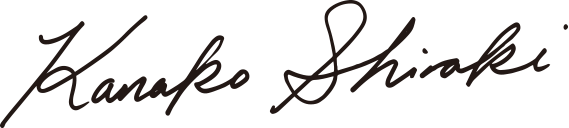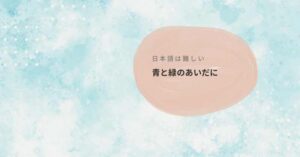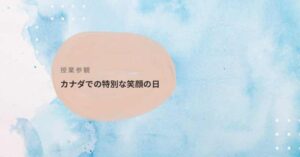こんにちは、白木です。
バンクーバーも春になってきました!
新入社員の皆様、入社おめでとうございます。
今回は、役員を務めている会社で、新入社員研修の一環として「業務改善提案」の演習を行いました。対象は新卒入社の25名。
ただレクチャーを聞くだけで終わるのではなく、実際に手を動かして考え、提案するという“実践型”の研修を企画しました。

Contents
講義→演習の流れで実施
まずは導入として、以下のような内容をレクチャーしました。
• プロジェクトマネジメントの基本
• 課題分析のフレームワーク(例:5Whys フィッシュボーン分析、AsIs-ToBeなど)
• ビジネスにおける提案書の構成と注意点
その上で、各自に業務改善提案書を一から作ってもらうという演習に進みました。
採点して感じたこと:伝わる提案の難しさと重要性
私自身、カナダの大学で実践的なビジネススキルを学ぶコースを履修しており、当時の教授が一つ一つの資料を丁寧に採点していた気持ちが今回とてもよく分かりました。
実際に提出された資料を見てみると──
• きちんとRFP(提案依頼書)に沿って構成できている人
• 問題の構造を捉え、論理的に改善案まで落とし込めている人
…こうした“ビジネスでそのまま使えるレベル”の提案ができていたのは、25人中3人でした。
とはいえ、伸びしろの宝庫
逆に言えば、多くの人にとっては今がスタート地点。特に今年は外国籍メンバーが多く、日本語の難しさも改めて実感しました。
例えば:
• 提案書とプレゼン資料の違いが曖昧な人が多かった
• 提案書は関係者以外にも“独り歩きする”文書であることの理解が足りない
• 同じ意味の言葉でも、ビジネスでは使わない表現が含まれていた
これらはすべて、今後改善していけるポイントです。
一人ひとりにコメントを返すことで得られる学び
今回は全員分の資料に目を通し、一人ひとりにフィードバックを記入しました。受け身で講義を聞くだけよりも、はるかに多くの気づきがあったのではないかと思います。
とはいえ、資料作成は数をこなしてナンボの世界。
• どうしたら読み手に伝わるか?
• どうしたら意思決定を後押しできるか?
• 成果や効果をどう“見える化”するか?
こうした問いに向き合いながら、経験と改善を重ねていくしかありません。
おわりに:新人たちのこれからに期待
今回の提案書にはそれぞれの個性や視点の違いが出ていて、読んでいて面白かったです。
資料作成って簡単そうに見えて、実はとても奥が深い。
この経験が、彼らの今後のキャリアの中でしっかりと“武器”になっていくことを願っています。
また次回も、実践的な取り組みをご紹介できたらと思います。