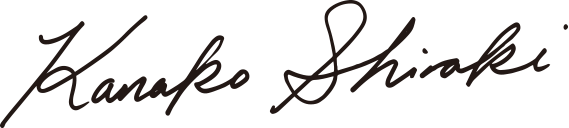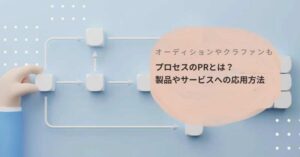ある日、友達が送ってきた動画がある。
「なぜ日本では“green light”を“青信号”と呼ぶのか?」という海外のショート動画だ。
動画の中の外国人の人が、全力で驚いている。「Why!?」って。笑いながら「lol!!!」って。
lolは、laughing out loudの略。
つまり、日本語でいうところの「(笑)」だ。
でも私には、外国語の「(笑)」のほうが、なんだか笑っていないように感じるのはなぜなんだろう。
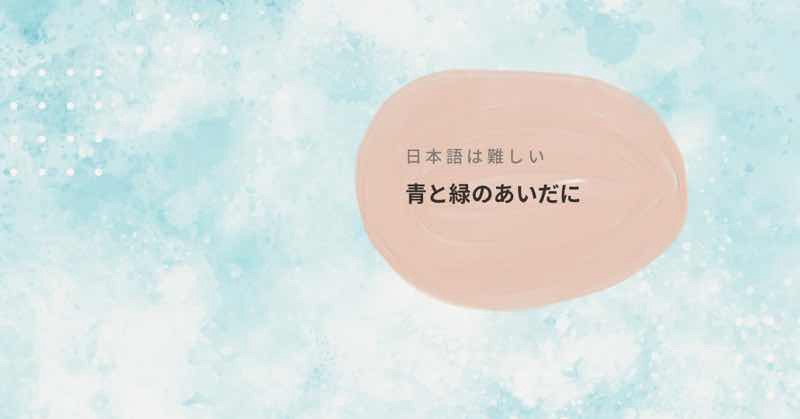
それはさておき、私はその動画を見ながら思った。
たしかに…「青信号」。あれ、どう見ても緑色やん。
green lightって言うやん。
英語でgreen onionは「青ネギ」、green appleは「青リンゴ」。
でも全部、日本語では「青」って呼ばれている。
え? なんで??
私は日本語話者であるにもかかわらず、全然説明できなかった。
ただ、「そう覚えるしかないんだよ」って、すごくつまらないことを言ってしまった。
そして、その自分のつまらなさが、少しだけ寂しかった。
でも、ふと気づいたのだ。
私たちは「緑を青」と呼ぶことはあるけど、
「青を緑」とは呼ばないのではないか?
AIに聞いてみた。今の時代は便利だ。疑問があれば、Google先生、もとい、ChatGPT先生が答えてくれる。
すると、昔の日本では色の分類がざっくりしていたらしく、緑は青の中に含まれていたという。
へえ、そうなんだ。
でもさ、青ネギや青リンゴは、まあ…見ようによっては青っぽい気もするけど、
信号はさあ、どう見ても緑よ?
あれは、明治以降にできたんじゃないの?
なのに、なぜ「青信号」なのか。
もうこれは、歴史とか習慣とか、そういう「しょうがない」の中に放り込むしかない。
言葉って、理屈じゃなくて、時代とともに「そうなってきたもの」なのかもしれない。
そう思ったら、ちょっとだけ優しい気持ちになった。
だって私、昔フランス語を勉強したとき、「80」の読み方で絶望したもん。
quatre-vingts(キャトルヴァン)、「4つの20」って。
何でやねん、と思った。
8×10でええやん、って思った。
でもそれも、「そういう言い方やねん」って受け入れるしかなかった。
言葉って、理屈よりも先に、そこにあるものなんだ。
説明できなくても、ちゃんと使えて、ちゃんと伝わる。
そのことが、ちょっと愛おしい。
今日も私は、青い空を見上げながら、
「あれ、でもこの空、ちょっと緑がかってるような…」なんて思って、
やっぱり日本語って不思議だなあ、って笑うのである。
lol。