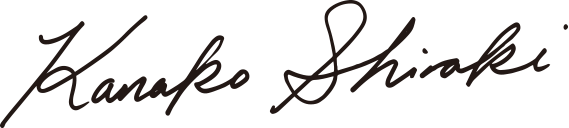先日、「海外市場における日本産商品の現状と課題」をテーマにした勉強会に参加してきました。お話しは、Valuablelink Consulting Inc. 代表鈴木美和さん。カナダ在住30年でご実家が岩手の農家さんだそうです。
カナダに住む私にとって、日本から遠く離れた地で日本産品がどのように受け止められているのかを知る貴重な機会でした。結論から言えば、「日本産=高品質・安心」というブランド価値は、残念ながらいま揺らいでいます。
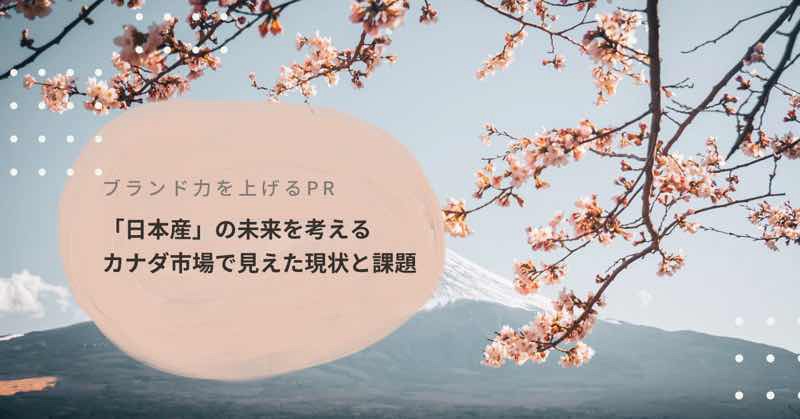
Contents
「日本語パッケージ」=日本産ではない
カナダのスーパーを歩くと、「日本語」が印刷された商品が目につきます。一見すると日本からの輸入品のように見えますが、よく見ると「Made in China」や「Product of Korea」といった表示が。つまり、日本の雰囲気をまとう“他国産品”が堂々と店頭に並び、消費者はその違いを見抜けずにいます。
さらに最近では、日本での規格外品を安価に買い取り、海外向けに再パッケージして販売する例も出てきています。これは「日本産ではあるが品質は低い」という、新たな混乱を生みかねません。
なぜ「本物の日本産」は売れないのか
一方で、日本から正規に輸出された商品は、たとえばみかん一個15ドル、箱で150ドルといったように非常に高価格で販売されています。それ自体は品質の高さに見合っているのかもしれません。しかし、その背景にあるストーリーや価値が消費者に伝わっていないため、結局は“安くて似たもの”に負けてしまい、店頭に並んでも売れ残ってしまうのです。
試食もなく、説明もなく、「高いから買わない」で終わってしまう――ここに、マーケティングとPRの不在があります。
ブランドを奪われた日本発祥の品々
シャインマスカット、いちご、和牛といった品々は、もともとは日本発祥でありながら、いまや他国でブランド化・量産され、世界に流通しています。特に韓国は、コロナ禍で飛行機が飛ばない中でもチャーター便を出してイチゴを輸出し、マーケットを確保しました。
これに比べ、日本政府の動きは遅く、また農家も国内需要である程度満足してしまっていたため、海外展開は後手に回った感が否めません。
輸出の壁と、生産者のジレンマ
とはいえ、生産者が個人や小規模で海外展開を進めるのは簡単ではありません。
市場調査や販路開拓の人材・知識が不足している 複雑な物流と中間業者によって利益が吸い取られてしまう 結果的に農家に利益が還元されない
これらの構造的な問題を乗り越えるには、「本物であること」を消費者に正しく伝え、プレミアムブランドとしての地位を築く必要があります。**ポルシェのように、「高いけれど理由がある」**と納得されるブランド作りが欠かせません。
海外市場での販売が、国内市場をも活性化する
「輸出は儲からない」と言われることもありますが、海外での高評価が国内のブランド価値を押し上げ、結果的に国内需要にも好影響をもたらす——そんな好循環も生まれます。
世界に向けて日本産品の魅力を伝える「アンテナショップ」的な場の必要性を強く感じました。そして、本来であればそれを推進すべきJETROのような組織が、その役割を十分に果たせていないのが現状です。
私にできること——現地にいるからこその視点で
今回の勉強会で特に印象に残ったのは、「和のテーマパークをバンクーバーにつくろうとしている」という講演者の鈴木さんの構想です。「行政を動かしたければ、まずは前例をつくる」という姿勢に共感しました。
そして私自身も、カナダにいるからこそできること——たとえば、市場調査、消費者ニーズのリサーチ、売場の分析などに取り組んでいきたいと強く感じました。
特にアメリカ市場は、関税や政権交代などの影響で進出が難しくなっている今、カナダはCPTPPなど自由貿易協定によってビジネスチャンスが広がっている恵まれた場所でもあります。
もし、「現地の声を聞きたい」「カナダでの市場調査をお願いしたい」という方がいらっしゃれば、ぜひお気軽にご連絡ください。一緒に、「本物の日本産品」を世界に伝える第一歩を踏み出せればと思っています。