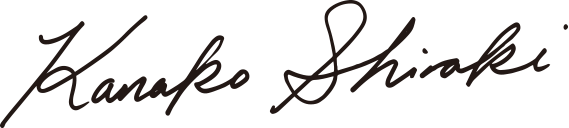新しい商品を開発していると、チームや関係者、あるいはユーザーの声に耳を傾ける機会が増えます。
それ自体はとても良いことです。ですが――意見を取り入れすぎるあまり、「全員一致病」に陥ってしまうことがあります。
実を言うと、私自身、誰かに意見をもらうと「取り入れないと失礼かな…」と悩むタイプです。
特に、自分よりも立場が上の人や尊敬する人の意見は、否定していいのかすら分からなくなってしまいます。
でも最近は、「意見を聞くこと」と「すべてを取り入れること」は違う、と思うようになりました。
商品のビジョンを軸にして、意見を“判断材料”として扱うこと。それが結果的に、商品をちゃんと届けたい人に届けるための道なんだと気づいたんです。

「全員一致病」って何?
「全員一致病」とは、すべての関係者の意見を取り入れようとして、誰にも響かない中途半端な商品になってしまう現象のこと。
いわゆる “Design by Committee(委員会による設計)” と呼ばれる状態です。
たとえば今、私が開発している商品にもこんなことがありました。
「この部分のデザインがとても好き!」という人がいる一方で、
「同じ部分がどうしても気になる。変えた方がいい」と言う人もいる。
どちらも正直な意見です。どちらも間違っていません。
でも、すべての声をそのまま反映していたら、最終的には“何がいいのか分からない”商品になってしまうのです。
商品は「誰のため」「何のため」にあるのか
商品開発で大切なのは、意見をまとめることではなく、方向性を明確にすることです。
誰のためにこの商品を作るのか? どんな課題を解決したいのか? 使った人にどう感じてほしいのか?
この軸がぶれてしまうと、良かれと思って加えた改善が、本来の価値や魅力を曇らせる結果になりかねません。
ビジョンをぶらさないために──PRFAQという手法
私が商品開発で特に重視しているのが、**PRFAQ(逆算型PR)**という考え方です。
PRFAQでは、「商品がリリースされたときに、どんな風にお客様に紹介されているか?」という理想の未来像から逆算して開発の指針を作ります。
たとえば、
プレスリリースでどんな悩みを解決したと書かれているか? お客様が喜んでいるポイントはどこか? どんなレビューがついているか?
といった“未来の声”を先に言語化することで、開発中の迷いやブレを防ぎやすくなるのです。
意見を活かしつつ、ビジョンに立ち返る
もちろん、ユーザーやチームの声に耳を傾けることは大切です。
ただし、そのすべてを「取り入れる」必要はありません。意見を“判断材料”にして、自分たちのビジョンに照らして取捨選択していくことが重要です。
商品開発は、誰かの「Yes」よりも、自信を持って「これがいい」と言える核を持つことが、最後にお客様に届く“強さ”につながります。
まとめ
「全員一致病」は、誰の心にも届かない商品を生むリスクがある 商品は「誰のために、何のためにあるのか」を問い直すことが大事 PRFAQを使えば、ビジョンを保ちつつ、ユーザー視点を見失わずに開発が進められる
「誰にでも良く見られる」ではなく、「ちゃんと届けたい人に届く」
そんな商品開発を、これからも続けていきたいと思います。