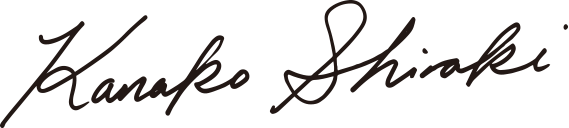夫がこの先が気になるから、Abema登録したのにカナダで見れなかった!と嘆いていた番組があるります。私も大好きな「しくじり先生」です。
スマホでダメでもテレビのアプリでは見れたので一緒に見ることにしました。
「えっ、そんな技術が20年前にあったの?」
驚くほど革新的なアイディアと技術力。しかしそれは、市場での成功を保証するものではありませんでした。プロダクト開発あるあるかもしれません。
今回は『しくじり先生 俺みたいになるな!!』で紹介された、セガ「メガドライブ」の失敗事例をもとに、プロダクトマーケットフィット(PMF)の重要性を掘り下げます。
どれだけ優れたプロダクトでも、「誰のために、何を届けるのか」がズレてしまえば失敗する。そのリアルな教訓を見ていきたいと思います。
お笑い番組のジャンルなのかもしれませんが、常にそこから仕事のことを考えてしまうのは私の職業柄仕方ないことだなと(笑)

Contents
技術はすごい。でも「誰も買えない・使えない」
セガのメガドライブは、当時のゲーム業界において非常に先進的なハードでした。
映像・音声表現、処理性能、拡張性……どれをとっても“技術者が夢中になるスペック”だったのです。
しかしその一方で、ユーザーからはこんな声が聞こえてきました。
「高くて買えない」「遊べるソフトが少ない」「なんでどんどん追加されていくの?」
事実、周辺機器が継ぎ足しのように発売され、メガCD、スーパー32Xなどが次々に登場。
それぞれが単体で高額であり、“メガドライブを持っていること”が前提となった拡張戦略は、新規ユーザーを大きく遠ざける結果となりました。
プロダクトマーケットフィット(PMF)とは何か?
PMFとは、「そのプロダクトが、明確なターゲットの“課題”や“欲求”にぴったりと合致している状態」のこと。
PMFが成立していれば、自然と売れ、口コミで広がり、継続的に愛される商品になります。
逆に、どれだけ高機能で優れていても、
• 誰のための商品かわからない
• 欲しいと思ってもらえない
• 続けて使いにくい
という状態では、市場に定着することはありません。
セガの「メガドライブ」はなぜPMFを逃したのか?
メガドライブの失敗は、PMFという視点から見るととても象徴的です。
ターゲットが不明確だった
子ども?大人?ゲームマニア?誰に届けたいかが曖昧。
生活者視点が抜けていた
高すぎる価格、魅力的なゲームソフトの少なさ、頻繁な追加投資。
「欲しいけど手が出せない」「持ってても遊びきれない」状態を生んでしまった。
技術力=価値だと信じすぎた
スペック競争に勝っても、ユーザーの満足に繋がらなければ意味がない。
セガが「作れるから作る」を優先してしまった結果、「売れる」ことから遠ざかってしまったのです。
だからこそ開発初期に“PR FAQ”を作るべき
私が商品開発支援で提唱しているのが、「まずPR FAQを作る」というアプローチです。
PR FAQとは:
• PR=リリース時に発信する「プレスリリース」
• FAQ=リリース時に寄せられるであろう「よくある質問」
これを開発初期に作っておくことで、
“この商品がどんな人に、どんな未来を届けるのか”を逆算して考えることができます。
PR FAQは、チーム全体でPMFを共通認識する「言語化ツール」であり、
市場に届くプロダクトを作るための“北極星”になります。
PMFを見据えた商品開発とは?
プロダクトマーケットフィットを目指す開発とは、「つくりたいもの」からではなく「求められるもの」から始まる開発です。
そのために必要なステップは以下の通りです。
1.ターゲットの課題を正確に把握する
2. 最初に“リリース後の未来”を描く(PR FAQの作成)
3. 仮説を立て、小さく検証する(プロトタイプ+ユーザーテスト)
4. 必要な技術とパーツを“絞って”届ける
5. 開発チーム全体が「ユーザーの成功」を目指す文化を持つ
これができれば、「メガドライブのようなしくじり」は避けられたかもしれません。
おわりに:セガの失敗は、私たちの学びにできる
セガは決して技術で劣っていたわけではありません。
むしろ、時代を先取りしすぎたがゆえの失敗でした。
でも、その「誰もが欲しい未来」が、「誰にも届かない商品」になってしまった。
それはとてももったいないことです。
だからこそ私たちは、技術や情熱を“ユーザーの視点”に結びつけることを忘れてはいけません。
そしてその第一歩として、「PR FAQ」を最初に描き、「市場で愛される未来」を先に作っておく。
プロダクトマーケットフィットは、運やタイミングではなく、設計できるものです。
しくじり先生、改めてみて面白いのに学べる、最高の番組ですね。